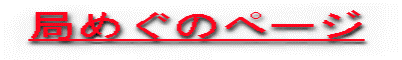
2000.10.29 update!
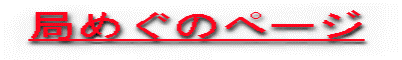
局めぐといっても、人それぞれやっている分野によっていろいろあります。
わたしの場合は以下の項目をやっています。
そのほか、郵便局マップ(自動機の設置・稼働状況があるとbest!)・郵便局だより・ 通帳袋・現金袋(局名入りだとgood!)などの収集も極力行っています。(後の整理が大変なんですが・・・。)
局めぐは時間が限られているため、「少ない移動時間でいかに効率よく回るか」が勝負(^^;;となります。 そこで、訪問する場所に応じて交通手段を選ばなければいけません。 わたしの場合は以下の交通手段を利用しています。
私の場合、局めぐするときはあらかじめ日程・回る地域を決めてから行っています。行き当たりばったりというケースはあまりありません。以下に局めぐの計画の立て方を挙げます。
一般に郵便局というのは普通何かへの「目印」となるものですが、私の場合は、郵便局に行くために、それがどこにあるのか探す必要があります。そのために地図が必要となってきます。
さて、 局めぐに使う地図ですが、主にS社の県別都市地図か県別マップルを使用しています。しかし、一般に郵便局というのは新設・移転が日常茶飯事に行われるため完璧に掲載されてはいません。まあ、それはしょうがないのですが、たまに移転とかが行われていないのに掲載されていないことがあり、当日気がついて慌てて探したり、後日気がついて泣きを見るケースがあります。(^^;;
そこでこのようなものについては他の地図を参照したり、逆に住所で追っかけたりして補いますが、それでも分からないときは、現地で「郵便局はどこですか?」と地元の方に尋ねるしかありません。(^^;;
このように、都市地図を用いてもなお、郵便局を探すのが困難なのが、北海道です。
一般的に北海道の地図は札幌市などの主要都市についてはほぼ全域の詳細がわかるのですが、道東・道北などになると縮尺の高い地図になってしまい、郵便局が確実に掲載されなくなるのです。そこで、北海道だけは地図の最後の砦、国土地理院の地形図を利用します。これを片っ端から買いまくってなんとか対応しています。ほんとに地図代はバカになりません。(^^;
でも、局めぐで一番ありがたいのは、その現地の郵便局でもらえる「郵便局マップ」ですね。(^^;;
さて局めぐをやるとき、たいていの局めぐらー(なんじやそりゃ)の方々は 「同じ局には2回以上同じ通帳で貯金しない。」と言うルールで局めぐをしていると思います。 わたしもそのルールで局めぐをしてきました。 しかし、郵便局というのは開局後、移転・改称・降格・昇格などがあり、「同じ局」をどう解釈すれば いいのかが難しくなってきます。 現にわたしも訪問した局で数局が移転改称してしまい、どうしようか悩んでいるところです。 そこで「1局の定義」というのを設けてそれに基づいて訪問局をカウントするようにしました。
定額小為替は一部の簡易局を除いて全国で購入できます。わたしが定額小為替を集め始めたのは去年の
10月で1000局達成の記念として50円の小為替を購入したのが始まりです。 ほんとうは受領書に押印してくれる為替印の収集が目的でした。
その後いくつかの局で購入していましたが、ある日その中にへんな記号が並んでいる
小為替があるのに気がつきました。Niftyのフォーラムでそのことを話したところ
「それは旧様式の小為替ですよ。」とのことでした。 どうやらこれは、言い方が悪いですが「売れ残り」というやつで、ごく一部の局でしか入手できないようです。
それからというもの、この旧様式の小為替を収集するのが主目的になってしまいました。(^^;;

これは定額小為替の本体です。上段が旧様式で、下段が現在の新様式の定額小為替です。
変な記号とは発行月をマークするためのものだそうです。 100円の小為替は旧様式はみどり色・新様式は黄色です。

←受領書はこのように縦型のカードホルダーに 収納して整理を行っています。この時はなんと旧様式3連荘でした。(^^;;
←この時は旧様式は真ん中の1枚しか当たり ませんでしたが、左の為替印は棒型と呼ばれるもので押印されました。これも一部の局でしか常時使用
していないので貴重なのです。(^^;;
1日ごと・年度ごとの訪問記録をまとめました。(^^;;
95年度・96年度・97年度・98年度・99年度 ・2000年度
都道府県ごと及びマルチごとの訪問数をリストにしました。
リストからは各道府県の訪問リストにジャンプできます。(一部)
![]() 都道府県別(含む北海道各マルチ)
都道府県別(含む北海道各マルチ)
![]() マルチ別詳細(除く北海道)
マルチ別詳細(除く北海道)
![]() 訪問マップ
訪問マップ![]() 県めぐリスト
県めぐリスト
鉄道沿線ごとに駅からの最寄り局をリストにしました。
なお、これは以前niftyのfcollg-17番でも発表したのと同じものです。
自動機預入をしてしまった「不完全訪問局」をリストにしてみました。(^^;;
訪問局数 501局(うち再訪19局(^^;;;;)
(イ)市部 264局 (ロ)郡部 237局 (ハ)マルチ 30 (ニ)宝 71局 (ヘ)ボーナス なし(T_T)
→ 29,321 ポイント
北端:北海道網走市 網走藻琴(8/1) 東端:北海道目梨郡羅臼町 岬町簡易(7/31) 西端:沖縄県那覇市 那覇中央(1/29) 南端:沖縄県島尻郡具志頭村 具志頭(1/29) 県別訪問内訳(10局以上のみ):(1)北海道 119 (2)長野 80 (3)京都 50 (4)熊本 41 (5)東京 30 (6)山梨 28 (7)沖縄 25 (8)三重 24 (9)大阪 19 (10)山形 13 (11)富山 11
![]() 局めぐのページへ戻る
局めぐのページへ戻る
(c)massan/1997-2001